
秋は空気が乾燥し、朝晩の冷え込みも感じる季節です。
東洋医学では、この時期は「肺」と関係が深く、
乾燥や冷えによって呼吸や肌、心のバランスが乱れやすいと考えられています。
この記事では、鍼灸師としての経験をもとに、
秋に整えておきたい体と心のケア方法を紹介します。
毎日の暮らしの中でできる小さな工夫が、心地よく過ごすための助けになります。
????秋の体と心に起きる変化
秋は、空気の乾燥とともに体の内側の潤いも失われやすくなります。
東洋医学ではこの時期に「肺」が活発に働くとされ、
呼吸や喉、肌の状態と深く関わっています。
私自身、秋になると痰が出ないのに喉に溜まるような違和感を感じることがあります。
これは乾燥によって体内の水分(津液)が減り、
粘り気だけが残るために起こる症状です。
さらに、喉の渇きや手指の乾燥が強くなり、
体の外側も内側も水分不足を感じやすくなります。
また、日が短くなることで気分の落ち込みを感じる人も少なくありません。
東洋医学では、秋は「悲しみ」の感情が強くなる季節とされ、
陽の光が減ることで心のエネルギーも沈みやすくなると考えます。
乾燥と気分の低下は、どちらも秋特有の変化です。
この自然な流れを理解し、バランスを整えることが、秋の養生の第一歩です。
????鍼灸の考える“乾燥”と“冷え”の仕組み
秋から冬にかけては、乾いた空気と低い気温が重なり、
体の働きがゆるやかになります。
まず、空気の乾燥によって体内の津液(しんえき)=体を潤す水分が不足します。
津液は、肌や喉、関節などを滑らかに動かすために欠かせません。
不足すると、喉のイガイガ感や手指のカサつきなど、
“体の乾き”としてあらわれます。
一方、「冷え」は気温の低下により体を温める力(陽気)が弱まり、
体温を維持しづらくなることで起こります。
陽気が不足すると血流が滞り、目の疲れ・肩のこり・手足の冷えが出やすくなります。
鍼灸の視点では、乾燥も冷えも「巡りの滞り」が原因です。
気・血・水(津液)の流れを整えることが、
体を季節の変化に順応させる鍵になります。
????日常でできる養生法(食事・生活・ツボ)
秋から冬にかけては、体を冷やさず、潤いを保つことが大切です。
ここでは、日常の中で実践しやすい養生法を紹介します。
????食事で整える
この季節におすすめなのは生姜(しょうが)です。
生姜には体を温め、冷えによる血流の停滞を防ぐ働きがあります。
スープや煮物などに少し加えるだけで、
胃腸の動きが良くなり、手足の冷えも和らぎます。
ただし、摂りすぎると体内の潤いを奪うため、
“温めながら潤す”料理がおすすめです。
れんこんや白きくらげ、はちみつなどを組み合わせると、
乾燥による喉の不快感も軽くなります。
????生活で整える
秋は呼吸が浅くなりやすい季節です。
1日の中で数分だけでも深呼吸を意識する時間を取りましょう。
呼吸を深めることで肺の働きが整い、
体の内側まで新しい空気が巡ります。
また、朝晩の冷え込みが強い日は湯船に浸かることも大切です。
熱すぎないお湯で体をじっくり温めると、
血流が全身に行き渡り、眠りの質も向上します。
????ツボで整える ― 太淵(たいえん)
秋の養生におすすめのツボは太淵(たいえん)です。
手首の横じわの上、親指側の少しくぼんだ場所にあります。
このツボは「肺の原穴」と呼ばれ、呼吸を深め、
喉の乾燥や軽い咳、体のだるさを和らげます。

両手の太淵を親指でゆっくり押しながら息を吐くと、
呼吸が整い、体の内側から温かさを感じられるでしょう。
????養生を続けるための心の整え方
養生は、特別なことを頑張る時間ではなく、
体と心の変化に気づく時間です。
季節の移り変わりを感じながら、
「最近乾燥してきた」「朝の冷えが強くなってきた」
といった小さな変化を見つけたら、
その都度対応していくことが大切です。
喉が乾いたら温かいお茶を飲む。
体が冷えたら湯船に浸かる。
気分が落ちたら、空を見上げて深呼吸をする。
こうした小さな対応の積み重ねが、
季節の変化に順応する“自然な養生”になります。
変化に逆らわず、流れに合わせて過ごすこと。
それが、鍼灸の考える「整える」という生き方です。

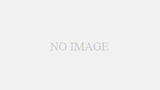
コメント