
「寝ても疲れが取れない」「常に体が重い」――そんな状態が続いていませんか?
東洋医学では、疲労を「気(エネルギー)の消耗」として考えます。
体を整え、巡りをよくすることで、自然と疲れは取れていきます。
この記事では、鍼灸師の視点から、疲れをやわらげる3つのツボと、
毎日の生活でできるセルフケアのポイントを紹介します。
????疲れが取れないのは「気の巡り」が滞っているから
東洋医学では、疲労は「気(エネルギー)の巡り」がうまく働いていない状態と考えます。
気は体の中を流れ、体温の維持や内臓の働き、心の安定にも関わる大切な要素です。
この気の状態には「実(じつ)」と「虚(きょ)」の2つがあり、
それぞれで体に現れるサインが異なります。
気が実(じつ)の場合は、気のエネルギーが過剰に動いたり、体の中にこもっている状態。
体がほてる、頭痛がする、そわそわして落ち着かないなどの症状が出やすくなります。
一方で、気が虚(きょ)の場合は、エネルギーが不足している状態。
体温が上がらず冷えを感じる、何もする気が起きない、
特に動いていないのに汗が出るなど、力の出ない感覚が続きます。
また、疲労が長引くと「痰湿(たんしつ)」と呼ばれる水分代謝の滞りも関係してきます。
気の力が弱くなることで体内の水分がうまく巡らず、
水が滞る → 体が重い・むくむ → さらに気が巡らなくなる、という悪循環に陥りやすくなります。
つまり、疲れが取れないときは「気が足りない」だけでなく、
気が滞っている、または痰湿が溜まっていることも多いのです。
疲労回復の第一歩は、エネルギーを補うだけでなく、気の巡りを整えることにあります。
????鍼灸師が選ぶ「疲労回復のツボ」3選
疲れが取れないときにおすすめしたいのが、
全身の巡りを整えてくれる3つの代表的なツボです。
????① 合谷(ごうこく)

)
親指と人差し指の骨が交わる部分にある万能のツボ。頭痛や肩こり、ストレス緩和に効果があります。
親指と人差し指の骨が交わる部分を軽く押すと、ズーンと響くような感覚があります。
5秒押して5秒休む、を3〜5回くり返すと、手先の血流が温まり、頭の重さがスッと軽くなります。
????② 足三里(あしさんり)
膝のお皿の下、外側から指4本分下の位置。全身の疲れに効く代表的なツボです。
気を補い、胃腸を整えるツボです。両手の親指でゆっくり押すと、全身のめぐりが良くなります。
足の疲れや食欲不振のときにもおすすめです。
????③ 豊隆(ほうりゅう)

すねの外側、膝と外くるぶしの中間あたり。体の中の“湿”をさばいて、重だるさをやわらげます。
足が重い・体がだるい時におすすめ。左右両方を軽くマッサージすると、全身がスッと軽くなります。
????ツボ押しは「少し痛いけれど気持ちいい」くらいの強さで。
呼吸をゆっくり整えながら行うと、気の巡りがよりスムーズになります。
????ツボを効果的に使うコツとセルフケア習慣
ツボ押しは、体が温まっているときが最も効果的です。
おすすめは、お風呂の中やお風呂上がりのタイミング。
お風呂に浸かっているときに、足三里や豊隆を軽くマッサージ。
血流が良くなり、むくみや重だるさが和らぎます。
お風呂上がりは、合谷や足三里を押しながら深呼吸を3回。
そのあと白湯を飲むと、内側からも体が整います。
ツボ押しは「続けること」が何より大切。
お風呂上がりの5分を“整える時間”として習慣にしてみてください。
????無理をしない「整える」疲労回復
疲労回復の鍵は「無理をしないこと」。
ツボ押しも休息も、どちらも体を整える大切な行為です。
そして、もう一歩進んで意識したいのが、
「元気なうちから整える」という考え方。
不調になってから整えるより、日頃から気の巡りを意識しておくことで、
疲れにくく、より元気に過ごせる体をつくることができます。
体の声を聞き、小さな整えを積み重ねていく――
それが、東洋医学でいう本当の「養生」です。


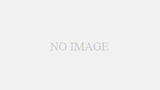
コメント