
病気の治療を続けていくうえで、医療費や通院の負担は大きな悩みになります。
私も、手術や抗がん剤治療が続く中で、経済的にも精神的にも限界を感じた時期がありました。
そんな時、支えになったのが「医療制度」や「公的支援」でした。
今回は、私が実際に利用した制度と、その中で感じたことをお伝えします。
????病気になって初めて知った「制度の壁」
初めて入院することになったとき、私は「治療費のこと」を深く考えたことがありませんでした。
ところが、入院の手続きでまず必要と言われたのが「保証金」と「健康保険の限度額認定証」でした。
保証金は数万円単位で、想像していたよりも大きな金額。
さらに、限度額認定証がないと、入院費をいったん全額自己負担で支払い、
後から払い戻しを受ける形になると説明を受けました。
そのとき初めて、
「病気の治療は、体だけでなく“制度”の知識も必要なんだ」と実感しました。
私の場合は、病院の事務スタッフの方が詳しく説明してくれ、
市役所に申請に行って数日後に証明書を受け取りました。
しかし、体調が悪い中での手続きは大変で、当時は右も左もわからず不安だらけでした。
こうした制度は、知っていれば助かるものばかりですが、
病気になってから初めて知る人が多いのが現実です。
あのとき、もし誰も教えてくれなかったら――と思うと、
「正しい情報が届くことの大切さ」を痛感しました。
????私が利用した主な制度
治療を続けるなかで、私が実際に利用して大きな助けになったのが
「限度額認定証」 と 「難病医療費助成制度」 の2つです。
どちらも申請の手間はありますが、知っているかどうかで負担がまったく違ってきます。
????1. 限度額認定証(高額療養費制度)
初めての入院のときに必要だったのが、この「限度額認定証」です。
健康保険証だけでは、入院費や手術費を一時的に全額自己負担し、
あとから払い戻してもらう必要があります。
しかし、限度額認定証を提出しておけば、窓口での支払いが自己負担限度額までで済む仕組みです。
手術や抗がん剤治療のように高額になりやすい治療でも、
この証を持っていれば1回の支払いは10万円以内に抑えられます。
現在では、マイナンバーカードに保険証を登録していれば自動で適用されるため、
申請の手間も減り、より使いやすくなりました。
????2. 難病医療費助成制度
私が発症した重症筋無力症は、指定難病に含まれています。
この制度を利用することで、入院だけでなく、
難病に関する通院治療や薬の費用も助成対象になります。
医療費の自己負担割合が軽減されるほか、
長期の治療でも経済的な不安を減らすことができます。
手続きは自治体ごとに異なりますが、申請時には主治医の診断書が必要です。
私の場合は、病院の医療相談室(ソーシャルワーカー)の方が書類の書き方や窓口を丁寧に教えてくれました。
長期治療では「医療を続けられる環境をつくる」ことも大切です。
この助成制度は、そのための大きな支えになっています。
????手続きの流れと注意点
制度は知っているだけで安心ですが、実際に申請してみると、
意外と時間がかかり、わかりづらい部分も多いと感じました。
????限度額認定証
私は協会けんぽの公式サイトから申請書をダウンロードし、郵送で提出しました。
申請から証書が届くまで約2〜3週間かかり、入院に間に合うか不安になった経験があります。
早めの申請をおすすめします。
現在は、マイナンバーカードに保険証を登録していればこの証が不要になり、
病院窓口で自動的に適用されるようになりました。
????難病医療費助成
都道府県によって手続きが異なり、私は神奈川県で申請しました。
県の公式サイトから申請書をダウンロードし、
世帯情報・マイナンバーカード・医師の診断書を添えて郵送。
診断書は都道府県指定の特別な様式があるため、必ず公式HPを確認することが大切です。
この助成は毎年更新が必要で、発行まで1〜2か月かかります。
書類の不足があるとさらに延びるので、提出前のチェックは入念に行いましょう。
????制度を使うことは「頼る」ことではなく「整える」こと
最初の頃は、正直「制度をたくさん使うのは面倒だ」と思っていました。
でも、実際に治療を始めると、“いくらかかるかわからない”という不安が想像以上に大きいことに気づきました。
その不安を少しでも減らすことで、治療に集中できるようになります。
制度を使うことは、誰かに頼ることではなく、
自分の体と暮らしを整えるための手段だと思います。
医療費を抑える仕組みを整えておけば、
「お金の心配」ではなく「回復」にエネルギーを注ぐことができます。
病気とともに生きるには、医療そのものと同じくらい、
「安心して治療を続けられる環境を整えること」が大切です。
制度を使うことは、そのための第一歩です。

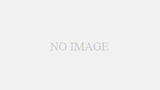
コメント